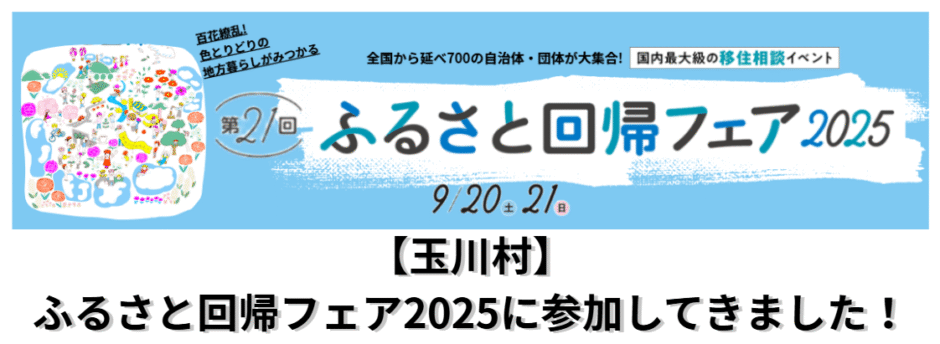迷う気持ちに寄り添う2日間
新卒で入社した会社を数年で退職することは、もう珍しいことではありません。
「このまま働き続けていいのだろうか」
「本当にやりたいことが見つからない」
「都会での生活に疲れてしまった」
そう感じて、立ち止まっている第二新卒世代は少なくありません。
あなたも今、次の一歩に迷っていませんか?
転職サイトを眺めてもピンと来ず、やりたいことはある気がするのに踏み出し方がわからない。社会人としてのスタートは切ったものの、将来像がまだはっきりしない ─ そんな悩みを抱えているのは、あなただけではありません。
そんなときに一度考えてみてほしいのが、地域おこし協力隊という選択肢です。全国の地域で若者が活躍しており、地方で暮らしながら新しい経験を積める制度として注目されています。そして、なかでも私たちの拠点である福島県・玉川村は、第二新卒世代にとって特にチャレンジしやすい環境を備えています。
私たちは2025年9月20日・21日、東京国際フォーラムで開催された「ふるさと回帰フェア2025」に2日間出展し、多くの方の“迷い”に耳を傾けました。終日ブースで対話を重ねる中で、玉川村と第二新卒の相性の良さをあらためて確信しました。本コラムでは、当日お伝えした内容を中心にご紹介します。
1.地域おこし協力隊とは?

地域おこし協力隊は、都市部から地方へ移住し、地域課題の解決や魅力発信に取り組む人材を自治体が委嘱する仕組みです。任期は概ね1〜3年(3年が主流)。「暮らし」と「仕事」を同時にデザインできるのが最大の特長です。
3年という期間は、短すぎず長すぎず、「地域に根を下ろして挑戦する」にはちょうど良い長さです。
活動内容は自治体によって異なりますが、主に次のような分野に大別されます。
- 農業や林業など一次産業の担い手育成
- 観光振興や地域イベントの企画運営
- 子育て・教育支援や福祉分野での活動
- 特産品の開発や地域ブランドの発信
- 空き家活用や移住・定住のコーディネート
- スポーツ振興や地域クラブ運営サポート
このように、地域ごとに課題やニーズが異なるため、ミッションの内容も多彩です。たとえば同じ「観光支援」であっても、ある地域では「伝統行事を継承する担い手」として、また別の地域では「インバウンド向けのPR担当」として求められるなど、役割は千差万別です。
地域おこし協力隊の最大の特徴は、暮らしと仕事を切り離さずに考えられる点です。
一般的な就職・転職活動では、まず「仕事」を決め、その後に勤務地や生活環境を合わせていく流れが一般的です。しかし協力隊では、「どんな地域で、どんな暮らしをしたいか」という視点から選択を始められるのが大きな違いです。
つまり、仕事の条件だけではなく、自然環境、地域の人との距離感、子育てのしやすさ、趣味やライフスタイルとの相性といった生活全体をデザインする視点が前提にあるのです。そのうえで、地域課題の解決や新しい挑戦につながる「仕事(ミッション)」がセットで用意されている。これはまさに「暮らし」と「仕事」の両輪を同時に考えられる、新しい働き方だと言えます。
第二新卒で「自分が何をしたいのか」「どんな生き方を選びたいのか」に悩んでいる人にとって、この制度はキャリア形成の再設計とライフデザインを同時に考えるきっかけになります。
地域おこし協力隊は「生活の安定を確保しながら挑戦できる制度」という側面もあります。報酬は自治体によって差がありますが、年額350万円程度が一般的です。加えて、住宅は自治体が用意した家を無償または低額で提供する場合が多く、家賃負担が大幅に軽減されます。(玉川村地域おこし協力隊は無償。)
また、活動に必要な経費(車両、PC、活動備品など)も自治体が予算として負担するケースが多く、「最低限の生活基盤は確保したうえで活動に集中できる」環境が整っています。都会の生活コストと比べると、地方は物価や住居費が安いため、給与水準以上の安定感を実感できる人も少なくありません。
そして、私たちの拠点である福島県玉川村では、
この協力隊制度を積極的に活用し、第二新卒の世代が安心して挑戦できる場を整えています。
2.玉川村に注目する理由
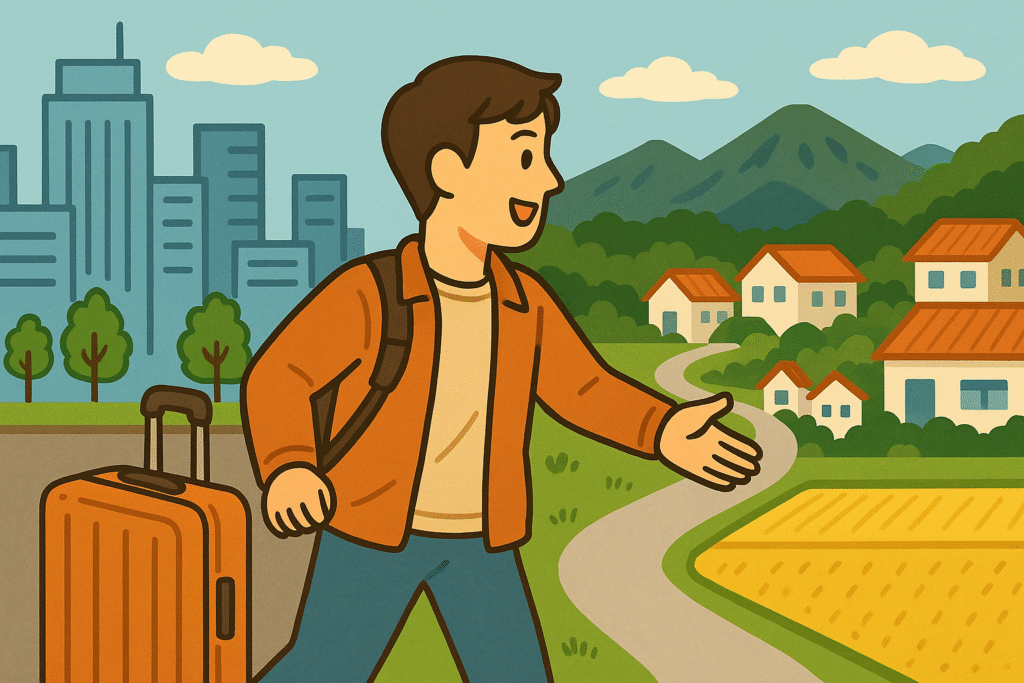
では、数ある地域おこし協力隊の中で、なぜ玉川村が注目に値するのでしょうか。
2-1.自然と風景の恵み
玉川村は四季折々の山並みや渓流に囲まれた自然豊かな村です。
春には新緑、夏には清流、秋には紅葉、冬には少ないですが雪景色と、都会では味わえない自然のリズムに寄り添った暮らしが可能です。
2-2. アクセスの良さ
地方暮らしの大きな課題の一つはアクセスです。
しかし玉川村は、その点でも優位性を持っています。村内には福島空港があり、大阪、北海道と直結。さらに、国道118号やあぶくま高原道路を通じて、郡山や白河といった都市圏へも短時間で移動できます。自然に囲まれつつも「都会とつながりやすい村」というのは、移住を検討する上で大きな安心材料です。
2-3. 特産品と地域資源を活かした挑戦
玉川村の特産品といえば「さるなし」です。この希少果実を使った加工品は、村のシンボル的存在であり、地域おこし協力隊の活動テーマとしても人気です。村は福島空港内に「空の駅」を設置し、観光客に特産品を直接届ける仕組みを整えています。商品開発やマーケティングに挑戦したい人にとっては、まさに格好のフィールドです。
2-4. 多彩なミッション
玉川村の協力隊はミッションの幅広さも魅力です。移住コーディネート、スポーツ振興、コミュニティ支援、地域ブランド発信、観光ツアー企画、移住関係など、関われるテーマは多岐にわたります。
小さな村だからこそ「やってみたいこと」をすぐに提案でき、実現しやすい土壌があります。
2-5. 成功事例と安心感
実際に、玉川村では自身の事業の立ち上げや、クラフトビール事業への挑戦、農業で成果を上げた協力隊員がいます。彼らは任期後も村に定住し、起業や地域活動を続けています。こうした成功事例は、これから挑戦する人にとって安心材料となります。
また現役隊員の多さも安心材料の一つです。福島県は全国で三番目に地域おこし協力隊の在籍数が多い都道府県なのですが、その福島県の中でも三番目に地域おこし協力隊の現役隊員数が多い自治体です。村では一番多いため地域おこし協力隊の制度を常により良い形にするべく挑戦を続けている地域でもあります。
サポートをする中間団体も入っており、その面からみても地域おこし協力隊のサポートに対して真摯に取り組んでいる村です。
2-6. 人の温かさ
そして何よりも強調したいのが、人の温かさです。
地域おこし協力隊として活動する中で、地域の人たちが自然に声をかけてくれる。「今日はどんなことをしてるの?」「野菜が取れすぎたからあげる」 ─ そんな日常的なつながりが、自分の居場所感をつくっていきます。
第二新卒でキャリアに迷っている人にとって、「受け入れてくれる地域の温度感」は大きな安心材料となるでしょう。
3.玉川村の地域おこし協力隊の魅力は多様で実践的なミッション

地域おこし協力隊は全国に数千人いますが、同じ制度でも「どの地域で活動するか」によって内容や経験は大きく変わります。だからこそ、候補地選びはとても大切です。玉川村で活動するからこそ得られる魅力を、具体的なミッションや現役隊員の声を交えて紹介します。
玉川村の協力隊の活動領域は幅広く、村の課題や可能性に直結したミッションが設定されています。代表的なものを挙げると次のとおりです。
3-1.スポーツ振興や健康づくりの推進
村では「たまかわ元気スポーツクラブ」を中心に、住民の健康づくりや学校部活動支援が進められています。地域おこし協力隊はこの活動に深く関わり、子どもから高齢者まで幅広い世代と交流できます。第二新卒の若い世代にとっては、体を動かすイベントや地域行事を企画し、地域住民と汗を流す経験が「自分の存在が役に立っている」という実感につながります。
また、玉川村は「日本一自転車が好きな村」としてサイクルビレッジたまかわプロジェクトを推進しています。その一環として、BMXをはじめとした多様なイベントを開催しており、全国的にも珍しい屋内型のBMX・スケートボードパーク「アーバンスポーツたまかわ」を整備しました。
この施設には、ボックスやレール、バンク、モヒカンといったストリートセクションに加え、2基のミニラン、ジャンラン、ウォールなど、豊富なセクションが揃っています。県内で唯一の本格的な屋内BMX・スケートボードパークとして、子どもから大人まで幅広い世代が利用できる環境が整っています。
3-2.地域ブランド「さるなし」を活かした商品開発やPR
玉川村を代表する特産品といえば、なんといっても「さるなし」です。さるなしはマタタビ科の果実で、見た目は小さなキウイに似ていますが、皮ごと食べられ、栄養価も非常に高い希少な果物です。ビタミンCはレモンの約10倍とも言われ、美容や健康志向の消費者から注目を集めています。
村ではこの「さるなし」を地域ブランドとして確立するため、ジュースやジャム、ワイン、リキュールといった加工品の開発を進めてきました。さらに、福島空港内の「空の駅」や道の駅、県内外のアンテナショップで販売するなど、販路を広げる取り組みも行われています。
地域おこし協力隊は、この「さるなしブランド」の担い手として、以下のような活動に挑戦できます。
3-3.子育て・教育支援(学習支援)
玉川村では、少子化が進む中でも子どもたちが安心して学び成長できる環境づくりが重視されています。その支援を担うのが「学習支援隊員」です。
具体的な活動は、昼休みに小・中学生の宿題や自主学習を見守ることから、高学年や中学生を対象にした受験・進学対策の補助まで幅広く、隊員の持っているスキルを活かした支援を行います。教員や保護者にとっては教育負担を軽減する効果があり、地域にとっては主に基礎学力向上による学力格差の是正や教育環境の安定につながります。
学習支援隊員は、先生や親とは異なる「お兄さん・お姉さん」のような立ち位置で、子どもたちにとって話しかけやすい存在です。その距離感が学習への意欲を引き出し、勉強に苦手意識を持つ子どもにも前向きな気持ちを与えます。
教員免許もすでに持っている第二新卒世代にとっては、自分の経験を活かしつつ、地域の未来を担う子どもたちを支える活動は大きなやりがいとなります。教員免許を持っていない隊員は三年間で資格取得に挑戦できます。小規模な村だからこそ一人の力が地域全体に響き、教育支援を通じて「確かに貢献している」という実感を持ちながら成長できるフィールドです。
3-4.移住定住促進の広報・イベント企画
移住希望者に向けたオンライン相談会や現地ツアーの企画・運営、SNSでの村の魅力発信も重要なミッションです。「地域おこし協力隊」という制度自体を広める活動でもあり、現役隊員が自分の言葉で「暮らしのリアル」を伝えることは、移住検討者にとって非常に説得力があります。
4. 第二新卒だからこそ地域おこし協力隊が合う3つの理由
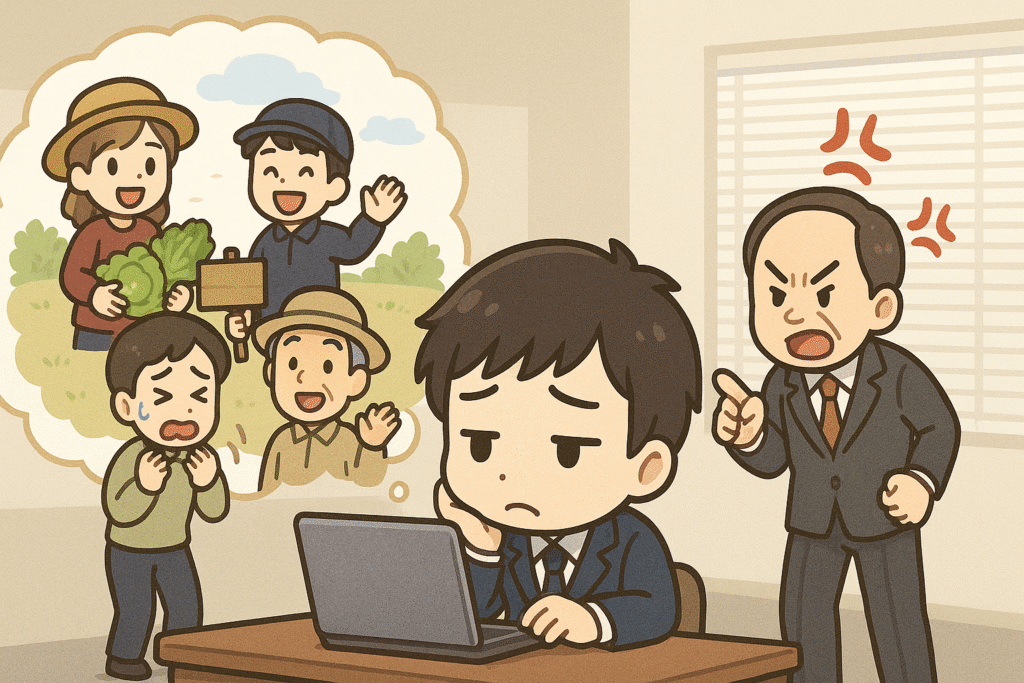
地域おこし協力隊は、幅広い世代に開かれた制度です。しかし、特に「第二新卒」と呼ばれる20代前半の若者にとっては、他の世代以上にフィットする面があります。会社を辞めたばかりで将来に迷いを感じている人こそ、協力隊の環境は「新しい自分を見つける舞台」となるのです。ここでは、その理由を3つの観点から整理します。
4-1. キャリアのリセットと再設計が可能
第二新卒の多くは、新卒で入社した会社に数年勤めたのち、「このままでいいのか」と迷いを感じています。会社を辞めるという決断は勇気がいる一方で、その後の選択肢に不安を抱える人も少なくありません。
地域おこし協力隊は、そうした不安を抱えた人に「一度立ち止まり、キャリアをリセットする時間」を与えてくれます。しかも単なる空白期間ではなく、地域のために汗をかき、人と関わり、成果を残せる“実働の場”です。
例えば、玉川村での活動はスポーツ指導やイベント企画、特産品PRといった具体的なテーマがあり、それぞれがキャリアの再設計に直結します。教育分野に関われば学校現場での経験に、商品開発に挑めばマーケティングや販売の実績に。3年間という任期を「社会にもう一度出るためのリハーサル期間」と捉えることもできます。
都会で同じ時間を過ごしても得られない経験値が、玉川村では積み上がっていくのです。
4-2. 地域での実践経験が次のキャリア資産になる
地域おこし協力隊の活動は、日々が「実践経験」の連続です。
たとえば地域イベントを企画する場合、計画立案から広報、当日の運営、振り返りまで、すべてを自分の手で行います。
都会の会社では部署ごとに分業される業務も、ここでは一人が幅広く担うことになります。
結果として、マルチスキルが自然に身につくのです。
玉川村では、小さな規模ゆえに住民との距離が近く、提案から実行までのスピードが速いことも特徴です。「やってみたい」と声を上げればすぐに挑戦でき、実際に成果を目にできる。
これは、仕事の成果が分かりにくい都会の職場では得難い経験です。
こうして培ったスキルや実績は、任期終了後のキャリアに直結します。
プロジェクトマネジメント能力、地域との協働力、情報発信力──。
これらは企業に戻るにせよ、起業を目指すにせよ、確かな武器となります。
「地域での挑戦が、その後の人生を支えるキャリア資産になる」──これこそが、第二新卒世代にとって地域おこし協力隊を選ぶ大きなメリットです。
4-3. 新しい仲間との出会いが自己成長を支える
社会人生活で一番つらいのは、「孤独」です。
特に第二新卒として会社を辞めたばかりの人は、自分の選択が正しかったのかどうか、周囲に理解されにくい状況に置かれがちです。
玉川村の協力隊には、同じように都市から来た若者や、すでに地域に根を下ろした先輩隊員、そして温かい村の人たちがいます。彼らとの関わりは、「一人ではない」という安心感を与えてくれます。
現役隊員の声にはこんなものがあります。
- 「最初は不安だったけど、イベントの準備で一緒に汗を流すうちに仲間になっていた」
- 「地域の人から『いつもありがとう』と声をかけてもらえたとき、やっとここが自分の居場所だと思えた」
第二新卒の世代にとって、こうした“仲間との出会い”は単なる人間関係以上の意味を持ちます。孤独や不安を和らげるだけでなく、自分の挑戦を後押ししてくれる存在となり、自己成長の大きな支えになります。
4-4.成長できる“実験の場”
玉川村の協力隊活動は、一言でいえば「自分を試せる実験の場」です。スポーツ、教育、観光、商品開発──さまざまなテーマに関わる中で、「自分はこういうことが得意なんだ」と気づけたり、「苦手だと思っていたけど、やってみたら意外に楽しい」と新しい発見があったりします。
社会に出てまだ数年、将来の方向性を模索している第二新卒世代にとって、これは大きな価値です。会社員としてただ目の前の仕事をこなすだけでは得られない経験が、玉川村には詰まっています。
そしてこれらの実験が自分のためだけでなく「地域のため」となっているチャレンジなのも大切なポイントです。
5. 子育て世代にとっても魅力的な環境
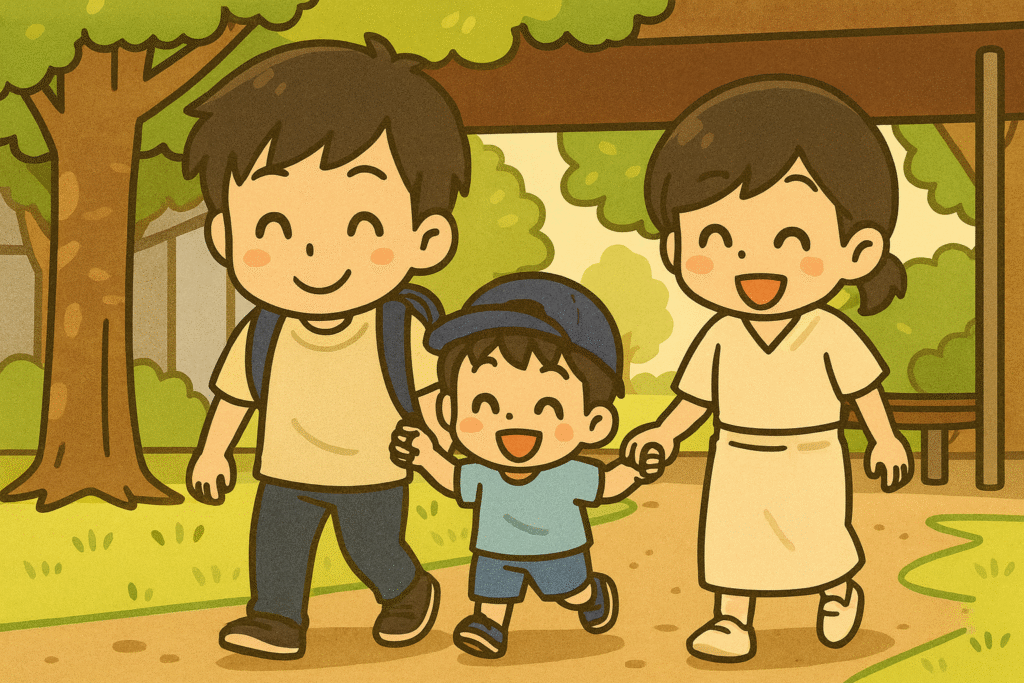
地域おこし協力隊は若い世代だけでなく、結婚や出産を経て「家族での暮らし」を考え始めた世代にとっても大きな魅力があります。玉川村はその点で、子育て世代が安心して挑戦できる環境を整えています。
5-1.教育・保育環境の充実
村内には保育所や小中学校が整備され、少人数ならではの自由度の高いきめ細やかな教育が行われています。
子どもたち一人ひとりに目が届きやすい環境は、保護者にとって大きな安心材料です。また、地域の人たちが学校行事や地域イベントを通じて子どもを見守る文化が根付いており、「地域ぐるみの子育て」が実現されています。
また、土地が広いためグラウンドでのびのびと身体を動かすこともできるのは、都会の小学校には難しいポイントです。
5-2.安心の生活環境
村はコンパクトながらも、生活に必要な機能が整っており、郡山市まで車で40分程度という立地から大規模な医療機関や買い物施設へのアクセスも良好です。都会ほど便利ではないように感じるかもしれませんが、基本が車移動なので大荷物を持って電車に揺られて帰ることも無ければ駐車場が見つからなくて途方に暮れることもありません。
5-3.子育て世代だからこそ地域に貢献できる
子育て世代の地域おこし協力隊は、自らの子育て経験を活かして地域の子育て支援や教育活動に関わることができます。放課後の学習支援や子育てサークルの立ち上げなど、同世代の親子を巻き込みながら活動することで、「地域で子どもを育てる仕組み」の担い手になることも可能です。
5-4.「親として」「協力隊として」成長できる場
子育てと仕事を両立するのは簡単ではありません。しかし玉川村の地域おこし協力隊活動は、地域に支えられながら「親としての成長」と「地域おこし協力隊としての挑戦」を同時に経験できる稀有な環境です。子どもの成長とともに、自らも地域の一員として成長できることは、他の職場ではなかなか得られない体験です。
玉川村は、第二新卒にとって「キャリア再設計の場」であるだけでなく、
子育て世代にとっても「家族とともに地域に根ざし、成長できる場」です。
地域おこし協力隊の活動を通じて地域に貢献することは、同時に自分の子どもに「地域に支えられながら育つ」という経験を与えることにもつながります。
6. よくある不安と答え

地域おこし協力隊に関心を持った人から必ず聞かれるのが「本当に生活できるのか」「任期が終わった後はどうなるのか」「地域になじめるのか」といった不安です。
これはごく自然な疑問であり、むしろ真剣に将来を考えているからこそ出てくる声でもあります。ここでは、玉川村での実情を踏まえながら、それぞれの不安と答えを整理してみます。
6-1.任期後のキャリアはどうなるのか?
地域おこし協力隊の任期は最長で3年間。
多くの地域おこし協力隊希望者にとって「その後のキャリア」が最大の懸念点です。
総務省の調査によると、協力隊経験者の約7割が任期終了後も活動地域に定住しています。玉川村でも、実際に任期後に村に残り、起業や就職に結びつけている隊員がいます。例として、特産品の「さるなし」を活かした商品開発を進めていた隊員が、任期後に地元事業者と連携し、村のブランド力向上に貢献している事例があります。
また、玉川村は起業支援制度や空き家活用支援を整備しており、独立して事業を始めるための環境が比較的整っています。もし村での起業を選ばずとも、地域おこし協力隊で培った「企画運営力」「地域協働力」「情報発信力」は都市部に戻っても高く評価されるスキルです。過去には村の役場職員採用試験を受けるという道もありました。
答え:任期終了後は、村で定住・起業する選択肢もあれば、都市部へ戻って新たなキャリアを築く道もある。いずれにしても、地域おこし協力隊での経験は“空白”ではなく“資産”になる。
6-2.地域になじめるだろうか?
「地域に溶け込めるのか」「よそ者扱いされないか」という不安もよく聞かれます。特に第二新卒や都会育ちの若者、子育て世代にとって、地域社会に飛び込むのは人生を賭けた大きな挑戦です。
玉川村では、地域おこし協力隊を受け入れる雰囲気があります。着任から三カ月も経てばいつから玉川村にいるんだっけか?というふうに聞かれてしまうほどです。
また、村の規模が小さいため、住民同士の距離が近く、名前を覚えてもらいやすいのも特徴です。村の祭りやスポーツ大会など仕事以外で村の行事に参加すれば、短期間で多くの住民と顔なじみになれます。
答え:玉川村は人との距離が近いため、自然に顔なじみが増え、地域の一員として迎えられる土壌がある。
6-3.給料だけで生活できるのか?
地域おこし協力隊の報酬は全国的に年間350万円程度が一般的です。都会の給与水準と比べれば高額とは言えません。そのため、「生活費を賄えるのか」という不安が出てくるのは当然です。
玉川村地域おこし協力隊の場合、住宅は村が準備してくれている民営アパートを活用でき、家賃は無償。都会であった「浪費」がないため普通に生活する分には十分な給料です。時には仲良しのおばあちゃんが取れ過ぎた野菜をお裾分けしてくれたりもします。
現役隊員の声として「都会にいたときは付き合いで参加していた飲み会や終電が無いから仕方なく行っていたカラオケのような出費が減り、むしろ貯金ができている」という例もあります。生活コストが低いことに加え、地域おこし協力隊の活動に必要な経費(車両、パソコン、備品など)は自治体が負担するため、自己負担は最小限で済みます。自分のやりたいことで地域貢献しながらお金をもらえる環境はストレスが少ないため自然と出費が減るようです。
答え:玉川村では住宅支援と生活コストの低さにより、地域おこし協力隊の報酬でも安定した生活が可能。むしろ都会暮らしより家計に余裕が出る場合もある。
6-4.家族や子育てとの両立はできるのか?
独身の若者だけでなく、子育て世代が地域おこし協力隊に応募するケースも増えています。「子どもを地方で育てたいが、教育環境や医療は大丈夫か」という声もよく聞かれます。
玉川村では、幼保連携型認定こども園や小中学校があり、少人数教育で手厚い指導が受けられます。医療については村内の診療所のほか、隣の須賀川市の公立岩瀬病院まで20分、郡山市や白河市の大規模病院へも40分程度でアクセス可能です。買い物も村内のスーパーで日用品が揃い、たいていの大型商業施設は車で1時間以内にあります。Amazonなども大体は翌日に届きますので重いものは通販にしたほうが楽ちんです。
子育て世代の協力隊は、自らの経験を活かして地域の子育て支援にも関わることができ、「親として」「地域おこし協力隊として」の両面で地域に貢献できるのが特徴です。
答え:玉川村は教育・医療・生活環境がコンパクトに整っており、子育て世代にとっても安心して暮らせる。
6-5. 孤独にならないか?
「見知らぬ土地で一人で暮らすのは心細い」という不安もあります。
玉川村では、地域おこし協力隊同士の交流はもちろん、現役隊員と仲良しの住民や役場職員は活動を支えてくれる体制があります。地域イベントに参加すれば他地域の地域おこし協力隊仲間が自然に増えたりもするため、自らが拒まない限り孤独を感じにくいのが特徴です。
ある隊員は「都会の会社員時代よりも人と会話する時間が増えた」と話しており、人とのつながりはむしろ濃くなる傾向があります。
答え:玉川村地域おこし協力隊は孤立せず、地域や仲間とのつながりの中で活動できる。孤独感よりも「居場所感」を得やすい。
地域おこし協力隊に関心を持つ人の不安は、「任期後」「地域になじめるか」「生活費」「家族」「孤独感」の5点に集約されます。玉川村は、これらの不安に対して制度や地域文化で明確な答えを用意できる環境を持っています。
- 任期後のキャリア → 定住支援と経験の資産化で安心
- 地域になじめるか → 小規模ゆえの距離の近さで早期に居場所が作れる
- 生活費 → 住宅支援と低コストで安定生活
- 子育てとの両立 → 教育・医療・買い物のバランスが良い
- 孤独感 → 地域や仲間との交流で解消
玉川村は、不安を希望に変えられる舞台です。
ここでの生活と活動は、第二新卒世代にも子育て世代にも「挑戦できる安心感」を与えてくれるでしょう。
7.次の一歩へ
ここまで玉川村の地域おこし協力隊について紹介してきましたが、最も大切なのは「読んで終わり」にせず、実際に行動へつなげることです。都会での暮らしに違和感を覚えている人も、キャリアの方向性に迷っている第二新卒も、子育て世代で新しい環境を探している人も─。
次の一歩を踏み出すためにできることを、具体的に整理してみます。
7-1.まずは知る
第一歩は「情報を集めること」です。玉川村の公式ホームページや協力隊の募集ページには、現在のミッション内容や活動紹介、先輩隊員の活動報告が掲載されています。
さらに、玉川村は毎年「ふるさと回帰フェア」などの移住イベントに出展し、現役隊員や役場担当者が直接相談に応じています。フェアでは「パンフレットで読んだだけでは分からなかったリアルな暮らし」が聞ける貴重な場となっています。
まずはこうしたイベントやWebサイトをチェックし、玉川村の地域おこし協力隊について知識を深めることから始めましょう。
7-2.話を聞く
次のステップは「直接話を聞く」ことです。
文章や写真では伝わらないニュアンスも、現役隊員や役場職員との会話で具体的にイメージできます。
たとえば、
- 「実際の一日の流れは?」
- 「任期後はどうしている人が多い?」
- 「村の人とどのように関わっている?」
といった質問をぶつけてみましょう。生の声からは、協力隊として暮らすリアリティが見えてきます。
玉川村には移住コーディネーターもおり、遠方に住んでいても気軽に相談できる環境があります。
7-3.体験してみる
「百聞は一見にしかず」。気になる地域があれば、まずは体験してみることをおすすめします。
玉川村では「おためしおこし隊」という短期体験制度を実施しており、実際に村に滞在しながら地域おこし協力隊の活動を体験できます。現役隊員と一緒に活動し、村の空気を肌で感じられることは、移住や応募を検討するうえで大きな判断材料になります。
「まずは数日間、村で生活してみる」─この体験が、不安を安心に変えてくれるのです。
7-4.行動に移す
情報を集め、話を聞き、体験してみて「やってみたい」と思ったら、次は実際に応募に踏み切ることです。
応募のプロセスは、エントリーシート提出 → 書類審査 → 面接 → 採用 → 委嘱 という流れが一般的です。玉川村の担当者は応募者の気持ちに寄り添い、三年後の卒隊まで見据えたミッションとのマッチングを丁寧に行います。
不安や疑問があれば、事前に何度でも相談可能です。
「地域になじめるだろうか」「家族で行って大丈夫だろうか」という質問も歓迎されています。
7-5.仲間をつくる
地域おこし協力隊として活動する上で大切なのは、仲間を持つことです。
玉川村には現役隊員だけでなく、過去に活動したOB・OGや移住者ネットワークがあります。
「困ったときに話せる人がいる」
「同じ立場で挑戦している仲間がいる」
そのつながりがあるからこそ、挑戦は孤独なものではなくなります。実際に、玉川村の地域おこし協力隊員はイベント運営や独自の体験プログラムを通じて横のつながりを育み、お互いに支え合っています。
7-6.行動は小さくても構わない
第二新卒や子育て世代にとって、移住や地域おこし協力隊への応募は大きな決断に見えるかもしれません。ですが、大切なのは一度にすべてを決めることではなく、「小さな一歩」を踏み出すことです。
- 公式サイトを覗いてみる
- オンライン相談を予約してみる
- 体験プログラムに参加してみる
このような行動が積み重なり、やがて新しい暮らしへの大きな一歩につながります。
玉川村で地域おこし協力隊として活動することは、単なるキャリア選択ではなく、「自分の人生を再設計する機会」です。そしてその一歩は、情報収集や短期体験といった小さな行動から始まります。
次の一歩を踏み出す準備ができたとき、玉川村はあなたを温かく迎える場所として、必ず力になってくれるでしょう。
9.結びに― 玉川村で、新しい自分を見つける
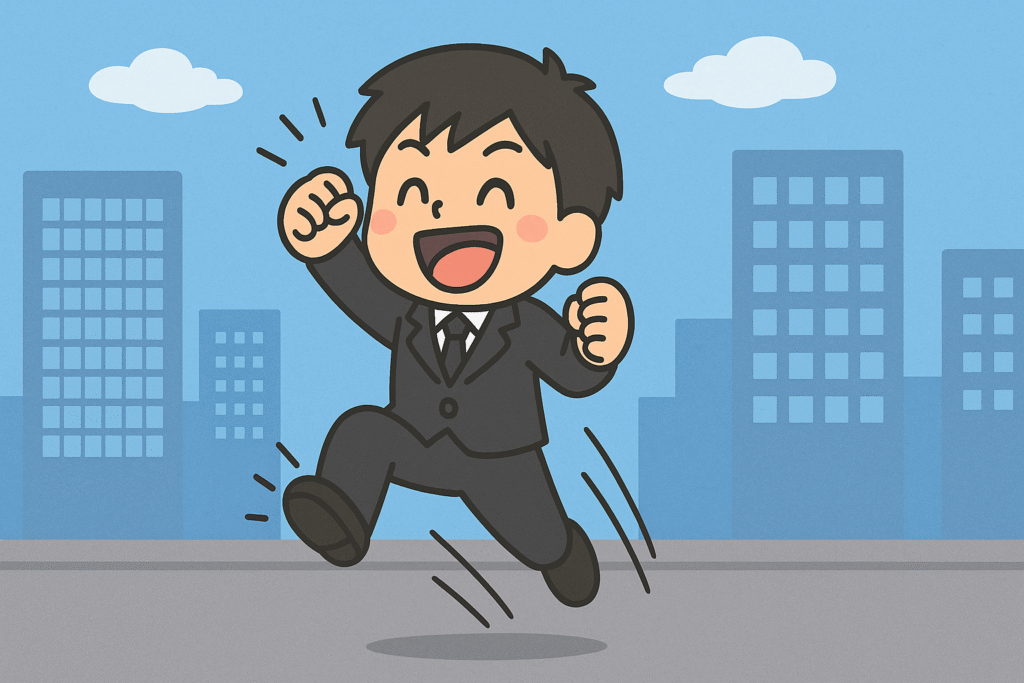
地域おこし協力隊という制度は、単なる「働き方のひとつ」ではありません。
都市部での暮らしや働き方に迷った人にとって、それは人生を再設計するための選択肢であり、同時に「地域に貢献しながら成長する」ための実践の場です。
第二新卒のあなたにとって、玉川村はキャリアを仕切り直す舞台となります。都会の会社員生活の中で感じた「このままでいいのか」「自分はパーツに過ぎないのではないか」という違和感を、地域での挑戦に変えることができます。スポーツ、教育、観光、商品開発 ─ どの分野でも、あなたの行動はすぐに地域に届き、住民の笑顔に直結します。その経験は、次のキャリアを築く大きな資産となり、今までにない自信を与えてくれるでしょう。
子育て世代のあなたにとっても、玉川村はかけがえのない環境です。子どもを自然の中でのびのび育てられる安心感、少人数教育による手厚い学び、地域ぐるみで子どもを大切にする文化。さらに、親としての経験を地域に還元しながら地域おこし協力隊として活動できることは、家族と共に地域に貢献する新しい生き方そのものです。
玉川村の魅力は、自然や制度の充実だけではありません。最大の魅力は「人」です。祭りやイベントで声をかけてくれる住民、日常的に気にかけてくれる隣人、共に活動する仲間たち。都会では得がたい人とのつながりが、ここにはあります。「あなたが来てくれて嬉しい」と言われたとき、あなたは村のことが大好きになっていることでしょう。
もちろん、地域おこし協力隊の道には不安もあります。
収入のこと、
任期後のキャリアのこと、
地域になじめるかという心配
教育の充実、
自治体とのマッチング。
ですが、玉川村はその一つひとつに答えを見出していっています。住宅支援や生活費の安さは経済的な安心を、起業支援や定住率の高さは未来への安心を、そして人の温かさは日々の安心を与えてくれます。しかし「誰でもなんでも助けてくれる」と勘違いしてはいけません。地域おこし(地域貢献人材)を行わない人には地域おこし協力隊は務まりません。
しかし三年間をしっかり過ごすことでこれだけは言えます。「玉川村でなら、新しい自分を見つけられる」 と。
大きな一歩でなくても構いません。まずは情報を集め、相談してみる。そして可能であれば「おためし協力隊」として短期間でも村を体験してみる。小さな行動の積み重ねが、未来を変える大きな一歩につながります。
あなたが今、都会で立ち止まり、将来に迷いを感じているなら。
あなたが今、家族と共に新しい暮らし方を探しているなら。
その答えの一つが、玉川村にあります。
地域のために力を尽くすことは、自分の人生を豊かにすることでもあります。
玉川村は、挑戦するあなたを必要としています。そして、その挑戦を全力で支えてくれる場所です。
どうか恐れずに、次の一歩を踏み出してください。
その一歩が、あなた自身と玉川村の未来を同時に明るく照らすはずです。
玉川村地域おこし協力隊募集
玉川村では、都市地域からの人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るとともに、村民の生活支援や地域の活性化に取り組んでいただける意欲のある協力隊メンバーを募集しています。活動内容や条件・待遇等は要綱に記載されておりますのでご確認ください。
募集する協力隊員(各1名)
1. 新体験アクティビティ創出支援隊員
2. アーバンスポーツ支援隊員
3. 新産業(養蜂事業)チャレンジ隊員【募集終了】
4. 提案型(フリーミッション隊員)
5. 美しい村づくり支援隊員【募集終了】
6. 移動図書・文化活動普及支援隊員【募集終了】
7. 元気スポーツクラブ活動支援隊員
https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/guide/plan/005311.html
玉川村おためしおこし隊
地域おこし協力隊の活動を体験!
現役隊員の活動やワークショップを通して、地域おこしのリアルな現場を体験できます。
3日間で「自分なら何ができるか?」を具体的に描いてみましょう。
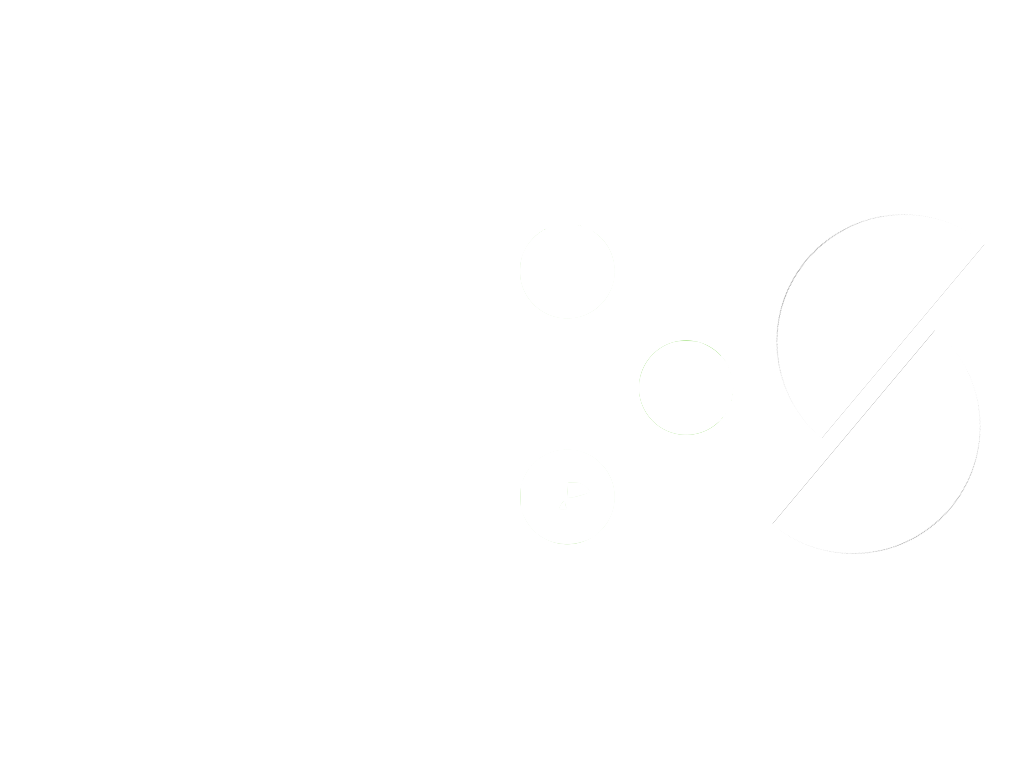 合同会社おこしたい
合同会社おこしたい